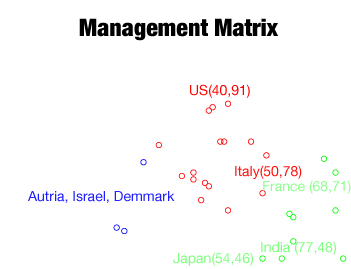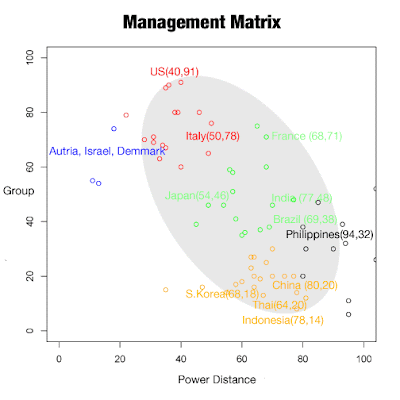7月1日6時、安倍首相は集団的自衛権の行使容認をする閣議決定を受けてについて記者会見を行い、各テレビ局が中継した。
これを受けてある新聞は「積極的平和に貢献する」と安倍首相を後押しした。一方、別の新聞は「将来戦争に巻き込まれる」と主張している。視聴者アンケートによっては「よく分からない」が最多数のものもある。最終的には「なんだかもやもやした」印象が残った。
「よく分からない」のは当然といえる。もともと「改憲」するつもりだったが、改憲に必要な大多数の賛成は得られなかった。そこで解釈改憲することに決めたのだが、これも公明党の反対を考慮して表現をすこし和らげた。
そもそも、説明から注意深く取り除かれている単語もある。
「密接な関係を持つ国」とはアメリカ合衆国(東洋経済オンライン「集団的自衛権、黒幕の米国が考えていること – 日米安保体制はますます米国の思うまま」)のことだ。だが、安倍首相の説明では最後まで特定の国名がでることはなかった。テレビや新聞は安倍政権のことばかりを伝えるが、アメリカについてはあまり触れられない。そもそも表面上、アメリカが日本にプレッシャーをかけたという事実もない。これがもっとも議論を難しくしている要因だろう。
この「よく分からない」はどのような影響を与えるのだろうか。原発についての議論を見てみるとわかる。日本には原発についての根強い反発がありデモも起きているが、政権には届いていないようだ。
では、推進派が勝利したかといえばそうでもない。日本中で原子力発電所は停止している。補償の問題で立地近隣の自治体が反対しており、手続きが滞っているからだ。近隣自治体は政府発信の情報を信用せず、わずかなリスクも許されないと考えているらしい。そもそも政府は信頼されていない。
政権は「よく分からない」という印象を残してしまったが故に、原発を推進することができなくなってしまったと考える事ができる。情報を隠したのは民主党政権だが、実際に影響を受けるのは自民党である。
このように「よく分からない」という印象はリスクに対する懸念をうみ、政策の実現に害をなすだろう。
集団的自衛権も同じようなルートをたどるだろう。軍事行動に参加したり、実際に自衛隊員の死傷者が出た時点で、支持率が急降下することが考えられる。それは安倍内閣かどうかは分からない。支持率急降下のリスクを怖れた政権は行使に対して慎重になるのではないかと思われる。
その時に拠り所になる憲法はない。明文化された憲法は「解釈やその時の事情でなんとでもなる」単なる文学作品に過ぎないからだ。