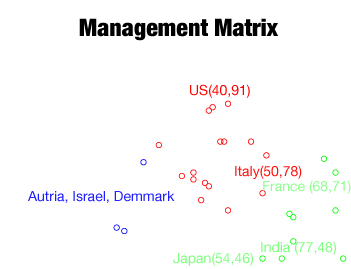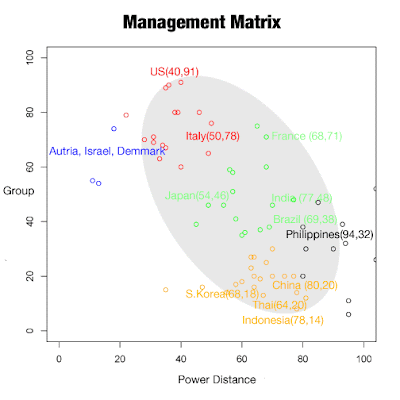北九州の出身である。東京で出身地を言うとたいてい「なんばしよっとか」と返ってくる。北九州市は福岡県の都市なのだが、違う方言を話す。しかし、東京の人には博多弁の印象が強いのだろう。博多弁は遠賀川以西から熊本あたりまで広がる別系統の方言だ。この中に東日本方言と同じ(ような)アクセントを持った地域とアクセントが崩壊した(ちょうど北関東なまりとおなじような感じだ)地域がある。北九州市から大分・宮崎あたりまでは別の言語がある。豊日方言と言われたりする。だから福岡県東部の出身者は「博多弁と北九州弁は違う」と思っている。瀬戸内海に面しているので、広島や山口の方言と近い。さらに九州には南に鹿児島弁がある。
ある本に、これを北九州語、西九州語と表現している学者の説を読んだ。日本人は遺伝子的に多様性が高いのだそうだ。これは世界各地から流れて来た人たちが吹きだまりやすい地域にあたるからのように思える。日本人は多様な民族の集まりなのだから、故に言語も多様なはずである、と主張する。
北九州方言は動詞に特徴がある。九州弁一般に言えるのかもしれない。「灯油がなくなりよー」と「灯油がなくっちょー」は違うことを言っている。「なくなりよー」はいまなくなりつつあることを意味する。そして「なくなっちょー」はなくなってしまったことを意味しているのである。だから、これを聞いた人は「いま灯油が入っているのか、入っていないのか」が分かる。なくなりよーは、なくなりつつあるのだから、まだ灯油は入っている。なくなっちょーは「なくなってしまった」であり、故に完了形なのだ。これは過去形に展開できる。なくなりよった、なくなっちょったである。だから、なくなっちょったは過去完了形であるといえる。
ところが、英語を習うとき、我々は「日本語には完了形はない」と習う。これは北九州方言の話者が「自分たちの言葉に完了形がある」ことを意識していないことを意味する。そして、この二つを違う意味として意識しないので、結果的に混用が起こると修正ができない。宿題を「いまやりよー」と「いまやっちょー」を同じ意味で使う人は多いのではないだろうか。しかしなくなるの活用を当てはめると正しくない。やりよーは「いまやっているよ」であり、やっちょーは「もうやってある」であるべきだ。しかし、区別は存在する。「もうやりよー」は「もう開始していていままさにやっている」という意味にしかなり得ない。一方、「もうやっちょー」は「もう開始していてすでに終っている」と解釈される可能性がある。
これは、北九州方言話者が、こうした区別のない標準語を覚える時、動詞が持っている機能をいったんバラしてべつの機能で置き換えていることを示している。この作業は意識的には行われない。「標準日本語には完了形がないから不便だ」と思う九州人はいないのではないか。
大学入学あたりで東京に出てくると、その後社会的に標準語が使えるようになる。しかし大学を卒業して東京に出てくると標準語が使えない人が出てくる。言葉は話せても社会的言語が獲得できない。鹿児島の出身者が小倉出身者を指して「あの人は単語の省略の仕方がヘンだ」とこぼしたのを聞いたことがある。この小倉出身者は大学卒業後地元で就職し、その後東京に転勤して来たのである。この鹿児島出身者はいま米系の企業で働いているバイリンガルだ。
これを説明するのに「東日本語」と「北九州語」は同じ系統の言語なので習得が容易だが、細かい差違は獲得が難しいとは言わない。北九州語は一般に方言扱いだからだ。しかし、この2つの言語を違う系統だと認めると、日本語が孤立的言語であるとは言えなくなる。同時に日本語の話者の数は減るだろう。1億人が同じ言葉を話しているという意味で、日本語は大言語だ。言語圏になれるくらいの規模は持っているのである。
よく沖縄の人たちが「本土扱いしてもらえない」ということがある。これは日本語が単一の言語であるという前提に立っているからだ。九州の人たちは「本土扱いされない」とは言わない。例えばお隣の長州弁は「ちょっと偉そうな」言語として認知されている。これは警官に長州出身者が多かったからだと言われている。これをひきずって「広島弁はやくざ映画で使われる」こうした諸方言は社会方言として認知されている。同じように静岡の影響を受けなかった(つまり江戸ではない)関東方言が「農村の言葉」として社会方言化している。つまり、日本語が(例え標準語であっても)多様な集まりであること意味している。
方言話者は外国語習得にも有利だ。九州方言の話者は文法的な特徴が標準語と違っている。しかし子どもの時からテレビで標準語に接している。基本的にこれを別系統の言語に当てはめるだけである。
一方、東京方言の話者は方言習得や別言語習得には気をつけたほうがいい。どうやら日本語には音声的な多様性もあるようだ。関西方言にアクセントの他に声調があるのは有名だ。これを声調を持っていない九州人や東京人が真似ると「変な関西弁」になる。そして関西人は自分たちが声調言語を話しているという意識はないので「その関西弁は正しくない」とは言えないのである。同じように北九州方言には撥音や濃音があるようだ。小倉弁は「っちゃ」が特徴的なのだが、若干喉が震える。「っとたい」の「た」も同様である。(喉に手をあててみるとわかる。喉をふるわせないで「たい」が言えないはずだ)撥音・濃音は朝鮮半島の言語に特有の特徴であり、こうしたつながりを認めたり、それを公にする学者はいないようだ。東京の人が九州の言語を真似すると平板に聞こえる。喉を使わないからだろう。そして九州人は濃音を意識できない。かなの記述でかき分けないからである。このように記述システムは発音の認知に影響を与えるが、だからといってその発音がなくなるということはないようである。同じように標準語でも「が」の鼻母音をかき分けないので、正しく発音されなくてもそれを指摘される事はない。
このように方言話者は音声的な違いを乗り越えている。この経験は英語習得に役立つ。また別の言語を学んでもいい。例えば英語を勉強するには最初に韓国語をやっておくと助けになる。韓国語には「お」にあたる母音が2つあり「う」も2つある。この違いを勉強しておくと、英語の曖昧母音などが発音しやすくなる。英語には母音文字が5つしかなく、そこに多様な母音を当てはめている。これを母音が5音しかない日本人が真似するので、日本人の英語は伝わりにくい。言語の多様性が大きいほど、別言語が学びやすくなる。日本語の常識をあてはめてしまうと、言語の習得はより難しくなるだろう。
さて、言語と方言にまつわる話はここまでだ。以下まとめる。
- 「日本語が単一言語である」かどうかは定かではない。見方の違いは、我々の民族観に大きな影響を与える。
- 私たちは細かな違いを意識しないで方言と標準語を使い分けている。この使い分け方は、英語や中国語などの他言語を習得するときに役立つ。
ここで問題になりそうなのは、多様性のある言語がどうして「同一言語」と見なされるのだろうかという点である。井上ひさしの国語元年を思い出したりするのだが、随分昔に読んだので機会があればまた読んでみたと思う。多様性があるのだが、違いを明確にせずやんわりと包括したのが「日本」という概念だったのではないかと思える。つまり、かつて我々の民族概念は私たちが思っているよりも遥かに柔軟なものだったのではないかと思えるのである。これを知らずに移民政策や日本人論を語ると結論を間違える可能性があるだろう。